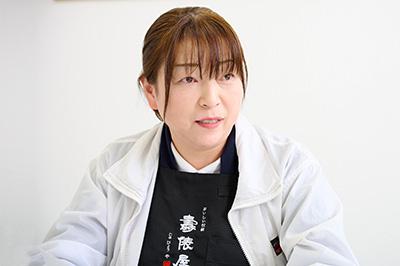守口漬の歴史には諸説ある。その名称は一説によると、天正13年(1585年)豊臣秀吉が大阪城と京都の往還で、淀川沿いの寒村「守口」で休憩の折、庄屋源兵衛が長大根の漬物を献上したところ、その風味が格別で大いに褒めたたえ、この地名を取って「もりぐち大根漬」(守口漬)と命名したことに由来するという。
その後、千利休らにより茶懐石料理の香の物のひとつになり、茶の湯の広がりとともに、京街道「守口宿名物」として知られるようになったとされる。(のちに大阪城下の発展とともに同地域での長大根の栽培は消滅、近年地域の特産への取り組みが進む)
さて明治に入り、愛知の実業家として知られる山田才吉氏が、美濃国(現在の岐阜県南部)で古くから栽培されていた細根大根を使い、酒粕とみりん粕を使った独自の漬け方を創作し、明治15年(1882年)、名古屋市中区にあった漬物店「きた福(喜多福)」にて「守口大根味醂粕漬け」として売り出した。この新しい商品の呼び名を、茶懐石料理の香の物(もりぐち大根漬)にヒントを得て命名。その略称である『守口漬』が定着し、現在に至っているとされている。